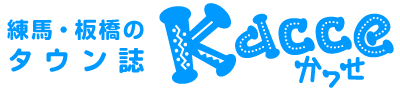※月刊Kacce2025年12月号(vol.503)掲載記事を再編集したものです。
二十四節気は、紀元前4世紀頃に中国の黄河中下流域で誕生したとされています。地球が太陽の周りを1周する1年を春夏秋冬に分け、それぞれの季節をさらに6つに分けて24の節気とし、より細やかに季節の移り変わりを知る手掛かりにしたものです。日本で体感する気候や季節感に合わない名称や時期があるため、日本では二十四節気のほかに土用、入梅、八十八夜などの雑節と呼ばれる独自の区分を取り入れています。ちなみに、二十四節気は中国の無形文化遺産に登録されています。
今月22日は二十四節気の冬至。最も昼が短く、夜が長くなる日です。「ん」の付く食べ物、レンコン、ニンジン、ナンキン(カボチャ)などを食べて、「運」を呼び込む験(げん)かつぎをしてみてはいかがでしょうか。
温暖化の影響で四季の移り変わりも怪しくなり、最近は春、夏、夏、秋、冬、冬のような体感ですが、西日本に分布する珍しい樹木「マルバノキ」(マンサク科マルバノキ属)を見かけました。別名はベニマンサク。紅葉と花を同時期に楽しめる植物です。図鑑などでは開花期が10〜11月となっていますが、植栽が関係しているのか、昨年は12月に花を見ました。樹形は株立ちで3m前後。葉は和名のように丸く、ハート型で長さも幅も10㎝前後、葉柄は6㎝前後です。花は赤く花弁は5個、2つの花が背中合わせに付きます。見かけた場所は、都営大江戸線光が丘駅A4出口を出て右へ進み、横断歩道を渡ってすぐの右手斜面です。


何かとあわただしい師走、ゆっくりとした気持ちで散歩をお続けください。
森野かずみ