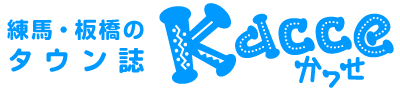※月刊Kacce2025年10月号(vol.501)掲載記事を再編集したものです。
今月6日は中秋の名月。平安時代に中国から伝わったとされる風習で、ススキと共に月見団子や里芋などを供えて収穫物への感謝を祈る旧暦8月15日の行事です。里芋のぬめり成分には薬効があり、脳細胞の活性化などが期待できるそうです。ちなみに今年は翌日7日が満月になります。
秋の公園散歩では、キノコをよく見かけます。弱った樹木や枯れ木、伐採された切り株に生える半円形のもの、樹林帯の林床に生える傘形や複雑な形のもの…といろいろありますが、公園などのキノコは見て楽しむものです。決して食べたりしないでください。おいしく食べられるキノコは栽培され市販されています。


今回は食べられないキノコを2つ紹介します。まず、サルノコシカケ科の「カワラタケ」。屋根の瓦のように重なり合って生えるのが特徴で、半円形から扇型をしています。傘は薄く、表面は黒や褐色など変化に富み、同心円状の環紋と孔口(こうこう)の白色やクリーム色とのコントラストが非常に美しく見えます。
2つ目は、マンネンタケ科の「コフキサルノコシカケ」。多年生で、ソメイヨシノやケヤキなどの広葉樹に多く発生します。傘の表面は灰白色〜灰褐色。胞子に覆われて、キノコの周りがチョコレート色になっていることがよくあります。孔口は白色〜帯黄色で、しばしば大型になるキノコです。


菌類は胞子をつくるために子実体という器官を形成しますが、そのうち肉眼で見える大きさのものを「キノコ」と言います。カエンタケのように触るだけでも危険なものもありますので、見るだけの散歩をお続けください。
森野かずみ